Vol.219 がたんごとん 店主 吉田 慎司さん

2025年4月、初めての著書が出た中津箒(なかつほうき)職人の吉田慎司さん。小樽・塩谷のDIYした住まいで詩歌に特化した書店「がたんごとん」を開いている。
[本日のフルコース]
中津箒職人が語る手仕事と詩歌、暮らしのこと
新刊発売記念「工芸と小樽の暮らし」フルコース
[2025.7.7]
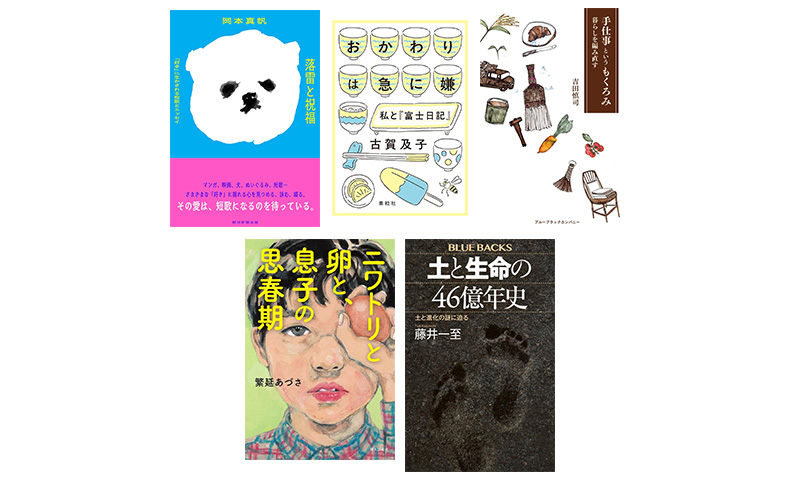
書店ナビ:2025年6月22日、小樽市東雲町に明治期から建つ石蔵が「◯」(マル)という文学スペースに生まれ変わり、柿落としに中津箒職人・吉田慎司さんの著書『手仕事というもくろみ 暮らしを編み直す』発売記念トークイベントが行われました。

小樽らしい坂道に面した石蔵「◯」(マル)は小樽で漁網や綿糸など漁業資材を取り扱う老舗企業の元倉庫。奈井江町の古道具「交点」が企画運営する。

イベント当日は吉田さんが焼いてきたカンパーニュやスペシャルティコーヒーなども用意され、参加者全員で蔵開きをお祝いした。パンがあまりにも美味しそうで皆がパチリ!

「がたんごとん」と白老町の「またたび文庫」さんも選書の出張販売を行った。

- 手仕事というもくろみ 暮らしを編み直す
吉田慎司 ブルーブラックカンパニー - 著者は明治時代から伝わる中津箒のつくり手。美大生から箒職人となるまでの道のりや、日々のものづくりと先達からの学びから見えてきた民藝論や工芸論、移住先の北海道小樽でのDIYによる住まい兼書店づくりなど2年間のWEB連載記事がこの一冊に。
書店ナビ:初の単行本となる本書を執筆した吉田さんは東京・練馬育ち。武蔵野美術大学時代に神奈川県中津村で生まれた中津箒の職人、柳川芳弘さんと出会います。
京都に暮らす柳川さんのもとで修行を積んだあとは国内唯一の中津箒メーカーである株式会社まちづくり山上に籍を置きながら個人の制作や展示会、ワークショップを展開。つねに手仕事と暮らし、社会との接点を考えてきたといいます。
(中略)僕は手仕事が好き、というよりは、手仕事に夢を見ている。それは端的に美しくて、人の心を癒やし、また、自然素材を活用して環境問題に訴求できるものでもある。労働としても自らの身体と直結した健やかなものだと思う。
『手仕事というもくろみ 暮らしを編み直す』130ページより抜粋
書店ナビ:札幌出身の妻・茜さんとともに「子育ては北海道で」と札幌に移住後、クリエイターマンションの一室に元書店員の茜さんが営む書店「がたんごとん」内にアトリエを構えた時期もありましたが、都市的な構造の札幌から「より手触りが感じられる場所」を求めて小樽・塩谷に築40年近くの屋根裏付き2階建てを土地ごと購入。 2021年6月から自身で改装した自宅1階で詩歌に特化した書店「がたんごとん」をオープンしました。 "生きるための道具と詩歌"というコンセプトについても新刊で次のように語っています。
僕がつくるものは道具で、最も生活に近い具体的なものだ。対して言葉は、最も抽象的で「生き延びる」だけなら不要なものだ。(中略)詩歌に出会い、「生きる」ための「道具」、そして呼吸をするための「詩情」を携えて生きたいと思った。それが今こそ、世界に必要なものだと、信じるようになった。
『手仕事というもくろみ 暮らしを編み直す』170ページより抜粋

吉田さんの自宅兼書店は道道956号小樽環状線沿い。JR塩谷駅から徒歩5分の距離にある。


120平米の敷地に畑やツリーハウスも作り、自給自足生活を実践する。
書店ナビ:新刊記念トークでは「この本の副題〈暮らしを編み直す〉は編集さんが付けてくれたものですが、まさにその通りで人は自然のようにゼロから生み出すことはできない。僕がホウキモロコシを編んで箒を作るように素材を組み合わせ、編み直すことで幸せに繋がるものを作っていく」と語った吉田さん。
「本のフルコース」の選書テーマを「工芸と小樽の暮らし」にしたのも「暮らしの場所や形が変わるとそこで出会う素材も変わる。小樽に越してきたことで自分の生き方や暮らしも今までとは違う編み方ができてきました」と語り、今の心情に照らし合わせた5冊を紹介してくれました。

玄関には展示会で一緒になった作家が描いてくれた中津箒のイラストが。

リビングの書棚は住まいや工芸に関わる本が並ぶ。元の家主が残した家具をそのまま活用しているため細部に昭和家具のやさしさが宿っている。
[本日のフルコース]
中津箒職人が語る手仕事と詩歌、暮らしのこと
新刊発売記念「工芸と小樽の暮らし」フルコース
前菜 そのテーマの導入となる読みやすい入門書
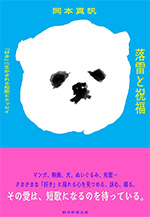
- 落雷と祝福
岡本真帆 朝日新聞出版 - 今をときめく「まほぴ」こと岡本さんが「好き」を滔々と語る短歌+エッセイ。岡本さんの短歌やエッセイには肩の力の抜けた等身大の在り方、のどかさや明るさがあり、好きなものを語るときにも誠実さや手応え、暮らしをガシガシと解きほぐしてくれる爽快感があります。
書店ナビ:岡本さんは2016年に「ほんとうにあたしでいいの? ずぼらだし、傘もこんなにたくさんあるし」という短歌を発表。これがTwitterでたちまち拡散され、下の句を各自がアレンジして自分のずぼらぶりを披露するネットミームに発展(ぜひググってみてください)。
それを受けてご本人がもう一度「ほんとうにあたしでいいの? ずぼらだし、凍ったいくら 風呂で溶かすし」と画像付きで投稿するというお茶目な本歌取りが話題になりました。
吉田:以前は、短歌は拡張高くて固いものだと思われていましたが、今はすごく手近なところまで降りてきた感があり、いろんな人に読まれるようになってきました。岡本さんはそこを切り拓いた若手の一人だと思います。
岡本さんのように自分の弱さや情けなさを表に出しながら、それを受け入れていくふくよかさみたいなものに皆が共感を覚えるのかも。
この本のように最近は詩人や歌人もシームレスにエッセイや小説を書くようになったと思います。わずか数文字について何週間も考え込む詩歌と、一筆書きみたいにぐいぐい書き上げていくエッセイや小説、そこを行きつ戻りつする気配が面白いですよね。
スープ 興味や好奇心がふくらんでいくおもしろ本
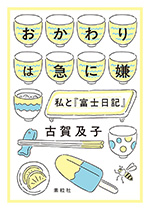
- おかわりは急に嫌 私と『富士日記』
古賀及子 素粒社 - 昭和期の日記文学の白眉『富士日記』を古賀さんが引用しながら、自らの暮らしに引き寄せていくエッセイ集。引き方、膨らませ方の巧みさで『富士日記』を書いた武田百合子さんのクレイジーさを際立てつつ、現在の古賀さんの生活との連携でなんとも楽しくなる心地がします。
書店ナビ:北海道民には『ひかりごけ』で知られる小説家の夫、武田泰淳と富士山麓で暮らした13年間(昭和39年~昭和51年)を夫人の百合子氏が「天衣無縫の文体」で映し出した『富士日記』。
中公文庫でも上中下巻のボリュームからどこを引用したのか、元デイリーポータルZの人気ライターだったエッセイスト古賀及子さんのセレクトが光ります。
吉田:『富士日記』をしっかり読み込み、さらにそれを今を生きている自身の生活や思い出に引きつけて書く、という非常に高度なことをごく自然にかつおもしろおかしく書けるところに古賀さんの力量を感じます。
百合子さんも古賀さんも決して特別なことを書いているわけではなく、ごく普通のことを書きながら皆が見落としそうな違和感や発見を素直に書いています。
今いろんな職種の人が書いたエッセイが流行っているのも、いわゆる主義主張が大きい"大文字の言葉"ではなく、こういう日常の出来事や等身大の人柄を大切にする流れができつつあるように感じます。「自分も書いていいのかな」という小さな芽がいろんなところから出てきて、その中で評価されたり新しい才能が見つかっていくのかもしれません。
魚料理 このテーマにはハズせない《王道》をいただく

- 手仕事というもくろみ 暮らしを編み直す
吉田慎司 ブルーブラックカンパニー - 版元のブルーブラックカンパニーが掲げる「社会デザイン」とは「システムに還元し得ない多様性(中略)の個別具体的な物語に共感」する学問で、この工芸的な響きに僕も共感を覚えました。「手仕事は表現ではない。世界との合意形成だと僕は思っている。」(あとがきより)
書店ナビ:フルコースに吉田さんの著書も入れていただきました。本書を「ものづくりの人が書く技術紹介や自伝的エッセイかな」と思って読むとちょっと違いますよね。
当時の自分の立ち位置が社会的にどうだったか、工芸やクラフトが社会活動史的にどう見られていたか、視点がつねに外に向いています。
吉田:大学の恩師が実践する研究者だったこともあり、自分の軸は「暮らしやものづくりを楽しもう」よりも「自分の周りの暮らしや社会を変えていこう」という思いが先にあります。
そのためにはまず「実践する」を自分のタスクにしていて、実践して初めて発言や仕事の説得力が変わってくるんだと思います。

吉田さんの作業場。取材中もあとで出てくるニワトリの鳴き声や道道を走る車の音が聞こえてきた。

ホウキモロコシの穂を束ねて「マルキ」を作る。「どの穂を使うか、どう組み合わせるか。箒づくりは選択の連続。昔の親方たちの仕事は"選別"だったそうです」
書店ナビ:特に第三章の民藝論や工芸論は参照資料の引用も多く、批評性が高い。読み応えがありました。
吉田:僕がいつもお伝えしていることに「価値と価値づけは違う」と思っていて。豊かな暮らしを一人で楽しみ実践すると本人はその価値を享受できるんだけど、言葉にして伝えない限り社会的な価値にはなっていかない。
暮らしも手仕事も可能な限り言葉にする、批評することであらためて文化として再評価され、価値づけがなされていくと考えています。
今は目立ってバズって消費されたら即座に消えていく、みたいな時代ですけど、そうじゃなくてちゃんと論拠に基づいた検証をして時代にアンカーを打っていく。そこをおろそかにしたくない。
この本を書いたことで、そうした日頃思っていることを一度形にすることができました。個人的にこれからは〈批評の時代〉がくるんじゃないかと感じています。
肉料理 がっつりこってり。読みごたえのある決定本
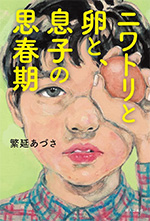
- ニワトリと卵と、息子の思春期
繁延あづさ 婦人之友社 - 小学生の息子が「ゲームの代わりに鶏を買って」と言い出し、共に暮らし、考え、締めて食べるまで命や自分に向かい合う暮らしを綴った本。誠実に生きる子どもたちの真っ直ぐさが胸を打ちます。読者も時に共感し、驚かされる大人たちの1人として参加できる感触です。
書店ナビ:著者の繁延(しげのぶ)さんは出産や狩猟、食や農をテーマに撮り続ける写真家で長崎市にお住まいだとか。この本は繁延さんファミリーの記録であり育児書でもありますね。

「うちもニワトリを育て始めてから暮らしが変わりました!」と吉田さん。ニワトリは雛や卵の生存率が低く、半分が大人になれないという。
吉田:ニワトリって食物連鎖では一番下にきますが、実は土も土中の虫も生ゴミもコーヒーかすもとにかく何かも食べてくれるすごい存在。
人間は本来、出産を除くと生物としては何かを生み出したり土に帰ることができないので自然の循環サイクルに入れない存在ですが、ニワトリを飼って卵を産ませて食べてまた土に帰すことでその循環の輪に入ることができる。今、周囲にもニワトリを推しまくっています。
繁延さんの本はタイトルにあるようにニワトリの話プラス「思春期」がテーマ。こういう本を婦人之友社が出していることに「さすが!」としびれます。
デザート スイーツでコースの余韻を楽しんで
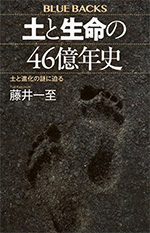
- 土と生命の46億年史
藤井一至 講談社 - 土の研究者が土と地球の起源から歴史を全力で描いた一冊。多数の論文を引きこんだドキュメント風で時にコミカル、リアリティを感じさせながらもすごく分かりやすく生命と自然の営みや関係、土の偉大さを読み解けます。土の上に生きるすべての人に読んで欲しい。
吉田:今ハマっているのが土なんです。全ての循環のベースが土。タイトルの「土と生命の46億年史」なんて考えただけでも気が遠くなりそうですが、藤井さんが2010年代20年代の最新の論文も引用しながら最終章の「土を作ることはできるのか」まで壮大な循環の物語を解き明かしてくれます。
うちのように自然栽培をする人や、環境問題、社会の在り方、人の生き方などを根本の根本から知りたい人におすすめです。

吉田家の暖房は小型のガスストーブもあるがメインは薪ストーブ。その薪も周辺の放置林を整備していると自然と薪が手に入るので暖房費ゼロ生活!
ごちそうさまトーク 人と幸せになるために胸を張れる暮らしがしたい
書店ナビ:実は吉田さんには札幌にいらした2019年5月に現代短歌のフルコースを作っていただいたこともありました。
Vol.154 箒のアトリエとお店「がたんごとん」 吉田 慎司さん [本日のフルコース] 箒のアトリエとお店「がたんごとん」の吉田さんが激奨! 「現代短歌の魅力にクリティカルKO!本」フルコース
書店ナビ:では最後の質問です。「自分のため」「人のため」「社会のため」という3つの円があるとしたら、今のご自分はそれらをどのように配置しますか。
吉田:「自分のため」「人のため」「社会のため」ですか…うーん……まあ、でも3つとも一緒ですね。全部重なる。本当に追い詰められたらわかんないですけど、でもやっぱりお腹が空いている人がいたら食べ物を差し出すと思う。
僕が大好きな竹細工職人の稲垣尚友さんは鹿児島県のトカラ諸島(臥蛇島、平島)で暮らしたことがある方なんです。そこでは島の誰かが夕飯に魚をさばいていたら、生垣の向こうから勝手につけ合わせの大根が飛んでくる、みたいな暮らしだと。
でも別にそこですぐにできた料理をお裾分けする的なお返しはしないんですって。それは島民同士が長いスパンで助け合って暮らしてきたから、その大根も何十年何世代も前のお返しかもしれないし、もっと先にお返しの時が来るかもしれない。
こういう市場経済の原理にのっとらない、人間関係の中で経済がまわっていく「人間経済」こそが実は真の効率化であり、最高のコスパなのではないか。最近ますますそう感じています。

ニワトリ飼育も薪暖房も不耕起栽培も箒づくりも詩歌の書店も「できるだけ小さい循環」を作ろうとしている。「自分だけ、じゃなくて人と幸せになりたい。それを実現するためにも胸を張れる暮らしがしたい」と手を動かしながら語ってくれた。
書店ナビ:新刊記念トーク会場になった「◯」でも今後、読書会や箒のワークショップなど中身の濃いイベントが開けそうですね。小さい循環の入り口に立つ「工芸と小樽の暮らし」のフルコース、ごちそうさまでした!

石蔵「◯」(小樽市東雲町9-15)へのお問い合わせは https://www.instagram.com/maru____jp/
吉田慎司(よしだ・しんじ)さん
1984年生まれ。東京・練馬にて育つ。武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業。2007年より株式会社まちづくり山上にて神奈川県で明治から伝わる中津箒作りを開始。制作、展示会、ワークショップ、講演、執筆などマルチに行う。北海道小樽市塩谷で自宅1階に道具と詩歌の店「がたんごとん」を開業。株式会社まちづくり山上 中津箒つくり手主任。LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 2017年度匠神奈川代表。2021年度日本民藝館展協会賞受賞。
